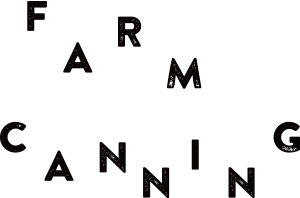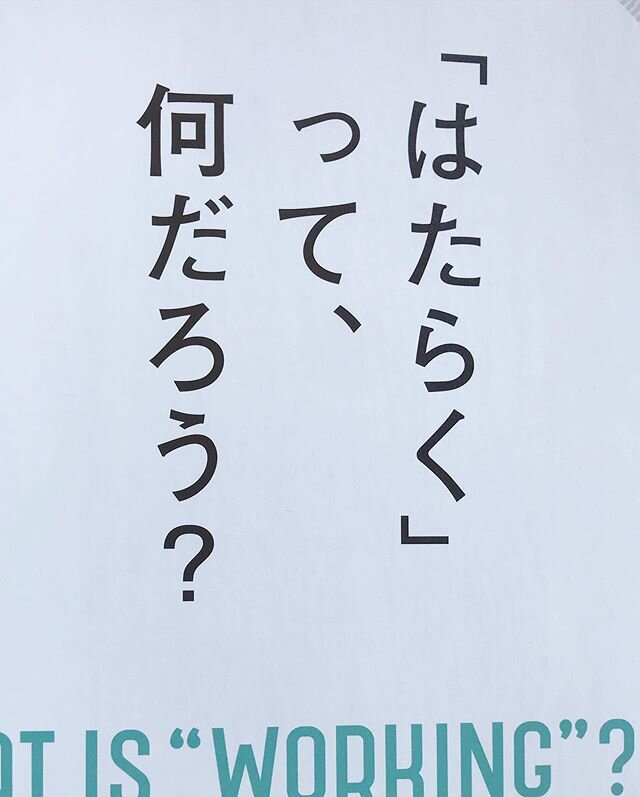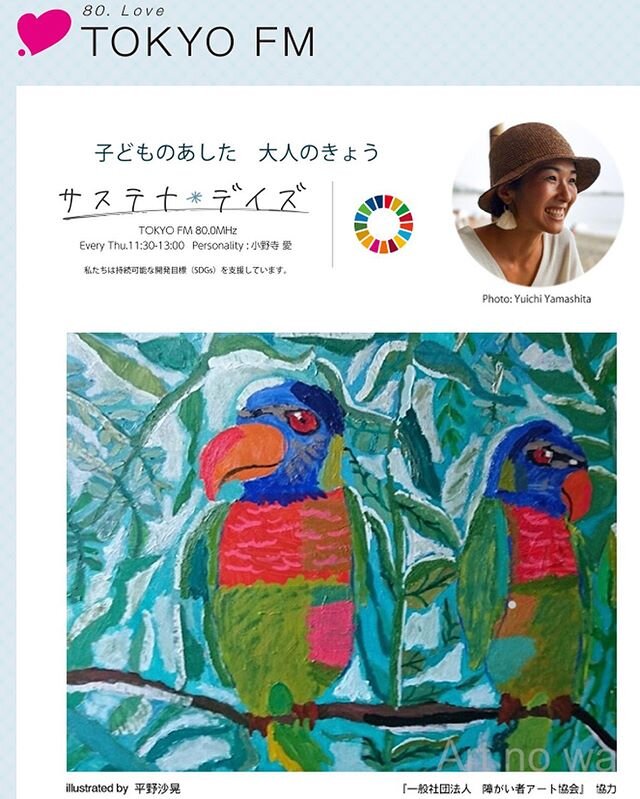みなさん、こんにちは。先月からコラムに挑戦し始めました、マイです!
コラム初心者ということで、何かテーマがあった方が書きやすいのでは?と「毎月の季節にちなんだあれこれ」を裏テーマ(?)にしようと密かに決めていました。
2月は節分のことにしよう!と思っていたのに、気づいたらバレンタインも過ぎている。。
ということで、節分は来年に回すとして、今回は先日仕込んだお味噌のことを。
今年で味噌作りは3年目。
「寒仕込みがいい」と聞き、毎年2月に仕込んでいたのですが、何が良いのか?調べてみました。
寒仕込みとは
字の通り、寒い時期に仕込むこと。
発酵がゆっくりと進むことで、旨味が増すとされており、風味豊かでまろやかな味噌ができあがるそうです。
、、、調べるもなにも、めちゃくちゃシンプルでした。
ちなみに、寒い時期以外に仕込んではいけないのか、ChatGPTに聞いてみたところ、
『現代では温度管理ができる環境が整っているため、春や秋などの他の季節にも仕込むことは可能です。
温暖な時期に仕込む場合でも、発酵が進みすぎないように温度管理をしっかり行えば、味噌をうまく仕込むことができます。最近では、温度を調整するために冷蔵庫や発酵器を使ったり、風通しの良い場所を選んだりする方法が取られることもあります。
まとめると、寒い時期がベストとは言われていますが、他の季節にも仕込むことができ、温度や管理の工夫次第で美味しい味噌を作ることができますよ!』
とのこと。ふーん、なるほど。ありがと。
浸水前でまだしわしわな大豆
約10時間後、水を吸ってぷっくりした大豆
【味噌の仕込み方】
大豆の準備
大豆を洗って、たっぷりの水に一晩浸けます。
大豆を茹でる
浸けた大豆を鍋に入れ、新しい水を加えて中火で煮ます。沸騰したらアクを取り、弱火で約2〜3時間ほど煮込みます。豆が簡単に潰れるくらい柔らかくなったら茹で上がりです。
大豆をつぶす
茹でた大豆を水分を少し残して、フードプロセッサーやすりこぎで粗くつぶします。完全にペースト状にしないように、少し豆の粒感を残すと、食感が良い味噌になります。
麹と塩を混ぜる
米麹と塩をよく混ぜ合わせます。
大豆と麹を混ぜ合わせる
つぶした大豆と麹・塩をよく混ぜ合わせます。このとき、手を使ってしっかりと混ぜるのがおすすめです。
容器に詰める
混ぜた材料を団子状にして、清潔な容器に投げ入れます!空気が入らないように、なるべくぎゅうぎゅうに、隙間なく詰めることが大切です。表面を平らにし、上から塩を少し振りかけると、カビ防止になります。
発酵させる
容器を涼しい場所で保存し、10ヶ月ほど発酵させます。
麹と塩をこすり合わせる(塩きり)
潰した大豆を加えて混ぜる
混ぜたもので団子を作って保存容器に空気が入らないように投げ入れていきます!思いっきり!
団子をならして、また団子を投げ入れていきます。
去年は 大豆1kg 玄米麹1kg 塩500g で、辛口のお味噌を仕込んだので、
今年は 大豆1kg 米麹1.5kg 塩500g で、麹を増やしてみました。少し甘みが出るかも?
仕上がりは4kgぐらいです。
ちなみに、大豆と麹は FARM CANNING でお世話になっている新潟の上野農場さんのものです。
お味噌作りは、量が多いので時間がかかりますが、大豆を茹でる際に圧力鍋を使うと時短になりますし、
作業自体はとってもシンプルです。
ご家族がいらっしゃる方は、みんなでこねこねすることで、自分たちに必要な常在菌が発酵の手助けをしてくれて、そのお味噌を摂取することでまた必要な常在菌を取り入れられる、なんてことも。
そうそう、同じ材料を使っても仕込む人が違えば味も変わるそうですよ!
菌って、深いですねぇ。
長くなりそうなので、菌についてはまたいつか。
ぜひみなさんで、楽しんで作ってみてくださいね!
Instagram
▶︎ FARM CANNING
▶︎ MAI